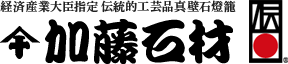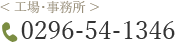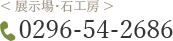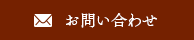先日、城里町の宝幢院様の本堂脇に「西円堂形燈籠・八尺」を据え付けをさせて頂きました。


この燈籠の本歌(オリジナル)は奈良県の法隆寺のもと西円堂の前にあった事から(西円堂形)と呼ばれている 昔から有名な石燈籠です
石材は 30~40年前まで真壁から産出されていた桃山石と呼んでいる今では貴重な石材です。
燈籠を据える前に筑波石を組み、燈籠を据えその前に火袋に灯りを入れる(火あげ石)と呼ぶ踏み石を据えて、ツワブキや南天・たまりゅう など足元に緑を植えて完成しました。



燈籠のベース(基礎)には、石を立てに打ち込み、ランマで転圧して地盤を締固めます。


笠の下端と受の上端は火袋の乗る部分には大入れと呼ぶ一段沈み込みを加工し、受と台座の竿が乗る部分はホゾを加工しています、この見えない所の手間が重要で、ずれを防止して地震での倒壊を防止します。


西円堂形は平成九年に制作したもので、かなり時代が付いて風格が出ていました、やはり苔の乗った筑波石とのバランスも良く、何年も前からそこに建っていた様になりました。


有り難う御座いました。